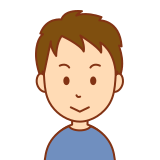
薬剤師さんって、ただ薬を渡すだけでしょう?
なんで先生に問い合わせたりするんだよ!
そう思われたことはありませんか?
実は私たち薬剤師には、処方せんを見ただけで”違和感”を察知する瞬間があります。
その”違和感”を感じたら、医師に確認の電話やFAXをしなくてはいけないのです。
それが「疑義照会(ギギショウカイ)」。
ときには医師がつかまらず、時間がかかってしまうことも…
でも、命を守る最後の砦になることもあるんです。
疑義照会とは?
「疑義照会(ぎぎしょうかい)」という言葉を、耳にしたことはありますか?
少し堅い響きですが、薬剤師にとっては日常業務の中でもっとも重要な仕事のひとつです。
疑義紹介とは、医師が出した処方せんの内容に誤りや疑問点がある場合に、薬剤師が医師へ確認する行為のこと。
たとえば、用量が多すぎる・飲み合わせが危険・同じ作用の薬が出ている―
そんな「おかしいかも?」という違和感を見逃さず、処方意図を確認します。
薬剤師法第24条でも「疑義があれば、医師等に問い合わせて確認しなければ調剤してはならない」と定められています。
つまり、疑義照会は薬剤師の“善意”ではなく、“法律で定められた使命”なんです。
医師が診察を行い、処方せんを書く。その後、薬剤師が内容をチェックして、問題があれば確認する。
この“ダブルチェック”の流れこそ、医療の安全を守るための大切な仕組みです。
医師も人間ですから、忙しい診察の中で入力ミスや薬の選択ミスが起きることがあります。
そんなとき、薬剤師が疑義照会を行うことで、誤った処方による副作用や重篤な健康被害を防ぐことができるのです。
たとえば、飲み合わせが悪い2種類の薬が出ていた場合。
または、同じ作用を持つ薬が重複して処方されていた場合。
薬剤師が気づいて医師に連絡することで、患者さんの命を救えるケースは少なくありません。
もちろん、医師に連絡を入れるのは少し勇気がいる瞬間です。
「先生を間違いだと指摘するようで気まずい」と感じることも、もちろんあります。
それでも薬剤師は、患者さんの安全を第一に考え、丁寧な言葉で確認を行います。
疑義照会は、医師と薬剤師の信頼関係の上に成り立つ“命を守る時間”。
大体はほんの数分のやりとりですが、総合病院など大きな病院の場合、医師が捉まらず時間がかかってしまうこともあります。
でも怒らないで……
その背後には患者さんへの想いと、医療を支えるプロとしての責任が詰まっているんです。
よくある疑義照会の事例は?
薬剤師が疑義照会を行うきっかけはさまざまですが、現場で特に多いのが
「飲み合わせ」「重複処方」「処方忘れ」「用量間違い」「日数の誤り」です。
どれも一見小さなミスに見えますが、放置すれば重大な健康被害に繋がる可能性があります。
まず多いのが、飲み合わせ(併用禁忌)。
たとえば、抗生物質のクラリスロマイシンと睡眠薬のベルソムラが同時処方されているケース。
鼻の調子が悪く、抗生物質のクラリスロマイシンが処方されるとします。
そこにこの患者さんは最近眠れないため、医師に相談して睡眠薬のベルソムラを出してもらう―
クラリスロマイシンとベルソムラは飲み合わせが悪く併用禁忌になっています。
一緒に飲んでしまうことで、睡眠薬のベルソムラの作用が強くなってしまい、眠気が強く出たり朝まで残ってしまったりして危険です。
薬剤師は患者さんの全処方を確認し、危険な組み合わせがないかを細かくチェックします。
次に多いのが、他院との重複処方。
高血圧の薬や胃薬などは、複数の医療機関にかかっている患者さんで重なって出されることがよくあります。
「先生が違うから大丈夫」と思われがちですが、同じ成分を二重で服用すると副作用が強く出ることも。
お薬手帳を見ながら、薬剤師が慎重に確認します。
また意外と多いのが、処方忘れ。
慢性疾患の薬で「いつも出ていた胃薬が今回はない」ということがあります。
患者さん自身も気づかない場合が多く、薬剤師が前回処方と照らし合わせて発見するケースも。
さらに、用量や日数の間違いもよく見られます。
小児や高齢者では体重や腎機能を考慮した調整が必要ですが、入力ミスや換算ミスで多すぎる量が出てしまうことも。
また、7日分のはずが70日分と入力されているなど、単純な入力ミスも少なくありません。
これらのどのケースも、薬剤師が気づいて疑義照会を行うことで、事故を未然に防ぐことができます。
一見小さな確認の積み重ねですが、そのひとつひとつが“患者さんの命を守るための仕事”なのです。
医師が間違えた実際の事例3選
医師も人間です。
診察や電子カルテの入力が忙しい中で、思い込みや似た薬剤による入力ミスはどうしても起こります。そんなとき、薬剤師の疑義照会が患者さんの安全を守る最後の砦になるのです。
ここでは、実際にあった3つの事例を紹介します。
まず一つ目は、「ノルバスク」と「ノルバデックス」の誤り。
ノルバスクは血圧を下げる薬、ノルバデックスは乳がんの治療薬です。
こちらも名前が似ており、カルテに入力するさい最初の3文字で薬を選ぶ場合が多いため、このような入力ミスが起こりやすいのです。
患者さんは高血圧の男性で、乳がん治療薬が処方されていました。薬剤師が確認しなければ、全く違った作用の薬を飲むことになりとても危ない事例でした。
二つ目は、「ストロメクトール」と「ストロカイン」の間違いです。
前者は駆虫薬で寄生虫の治療に使われますが、後者は胃痛などに処方される薬。
名前が非常に似ているため、入力時に選択ミスが起こりやすい組み合わせです。胃痛の患者さんにストロメクトールが出ていたら…と考えるとぞっとします。薬剤師が気づいて疑義照会を行い、すぐに訂正してもらいました。
三つ目は、タガメットとタケキャブの重複処方です。
整形外科で胃薬でもあるタガメットが処方され、内科ではタケキャブが出ていたというケース。
タガメットは胃薬なのですが、整形外科ではよく関節の石灰沈着による炎症で処方されます。
こういった胃薬とは別の作用がある薬だからこそ、他院からの胃薬と重複してしまうケース。
しかしどちらも胃酸を抑える薬なので、重複すると過度な胃酸抑制で消化不良などのリスクが高まります。薬剤師の疑義照会により、内科のタケキャブが中止になりました。
このように、処方せんやお薬手帳を丁寧に確認することで、患者さんの健康を守ることができます。疑義照会は「面倒な確認」ではなく、「命を守る行動」なのです。
まとめ〜疑義照会は「命を守る時間」〜
疑義照会は、単なる確認作業ではなく「患者さんの命を守る時間」です。
薬剤師が1枚の処方せんをじっと見つめているその時間に、間違いを防ぎ、誰かの健康を守る力があります。
ときには疑義照会に時間がかかり、窓口でお待たせしてしまうこともあります。
しかしその「少しの時間」が、重大な事故を防ぐ大切な確認の瞬間なのです。
どうか、「まだ薬ができないの?」と焦らず、薬剤師の背中を少しだけ見守ってください。
私たちは、患者さんの安全のために今日も処方せんと向き合っています。
たった一つの疑義照会が、誰かの未来を守ることにつながる——その想いを胸に、これからも仕事に取り組んでいきたいと思います。
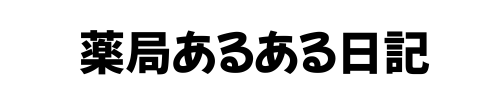
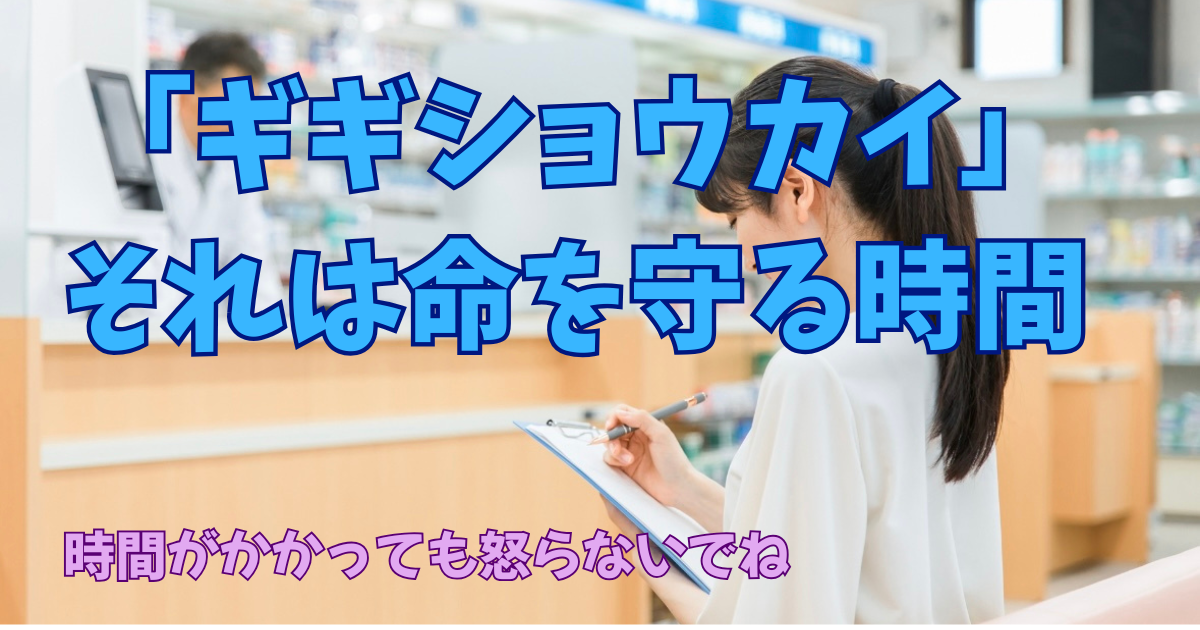


コメント